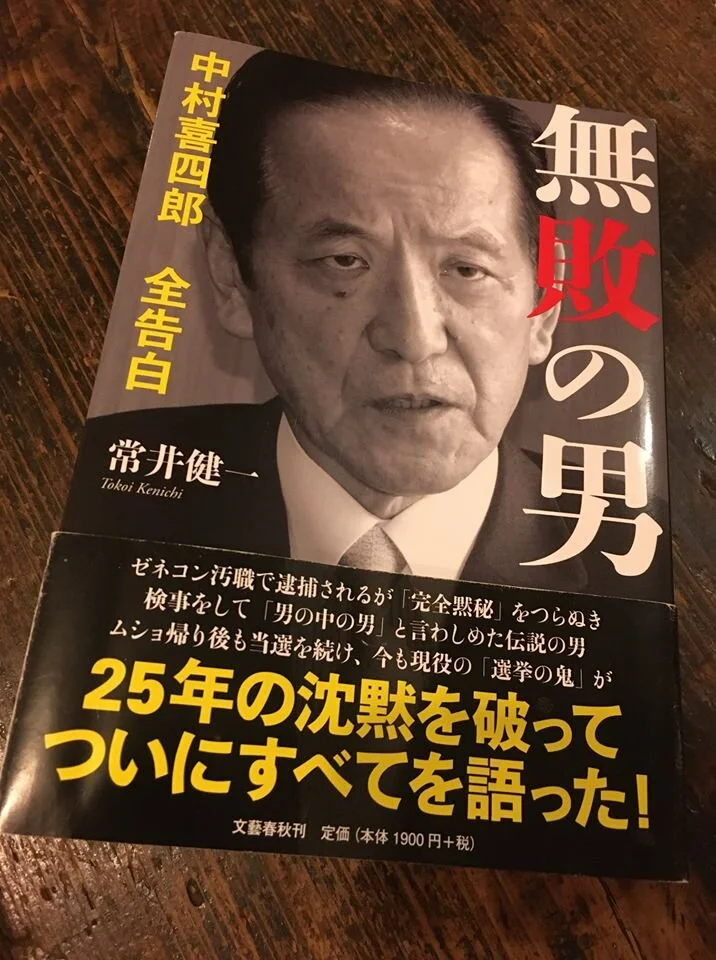今日の週刊文春の記事「森友自殺財務省職員遺書全文公開」(相澤冬樹さん筆)
を読み、こんな人たちが財務官僚として社会の中枢にいるのかと思うと本当に腹立たしくなった。
自分自身、おそらくそういう人たちと同様に、受験勉強にエネルギーを使い、結果としていまの学歴社会でうまく立ち振る舞ってきたという自覚がある。でも、傲慢に聞こえかねないことを覚悟で言えば、そういう点において恵まれた環境で生きてきた自分自身について、居心地の悪さというか、後ろめたさみたいなものがあり、同時に、自分がそういう境遇を利用して生きていることについて自覚的でなければいけないと思っている。
うまく言えないけれど、おそらく多かれ少なかれ彼らと近い環境にいた時期がある身として、いったいどうして、そんな生き方をして平気でいられるんだ、という気持ちがある。勉強して、エリート街道みたいな人生を進んで権力を得て、その挙句にその立場を利用して改ざんや隠ぺいをして、自分より立場の上の人にだけはこびへつらって、責任は自分の部下に押し付けて。なぜ恥ずかしくないのだろう。なぜ平然とその立場にい続けられるのか。
こういうことを書くこと自体に、自分の傲慢さのようなものがあるのかもしれず、その点も含めて色々自覚的でなければと思うのだけれど、赤木さんが遺書に書いている財務官僚の面々などに、自分もある種近しい立場的なものを感じるだけに、無性に腹立たしく、悔しく、彼らに、本当によく自分の人生を省みてほしいと思う。
余計な内面を変な形で書いてしまったかもしれずですが、でも、記事を読んで本当に怒りが沸きました。この記事の訴え、亡き赤木さんの声が無視されるような社会には生きていたくないな、と心底思う。