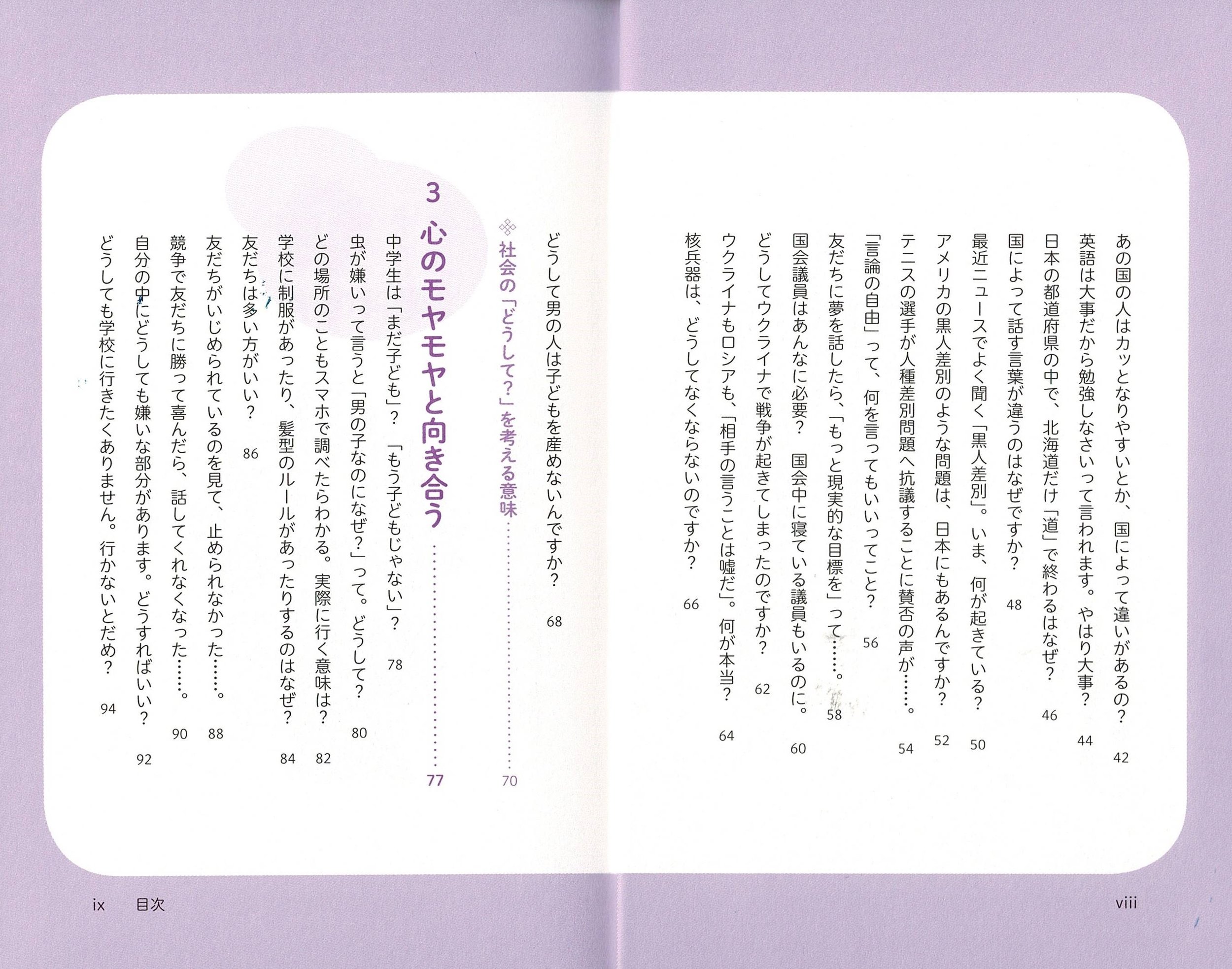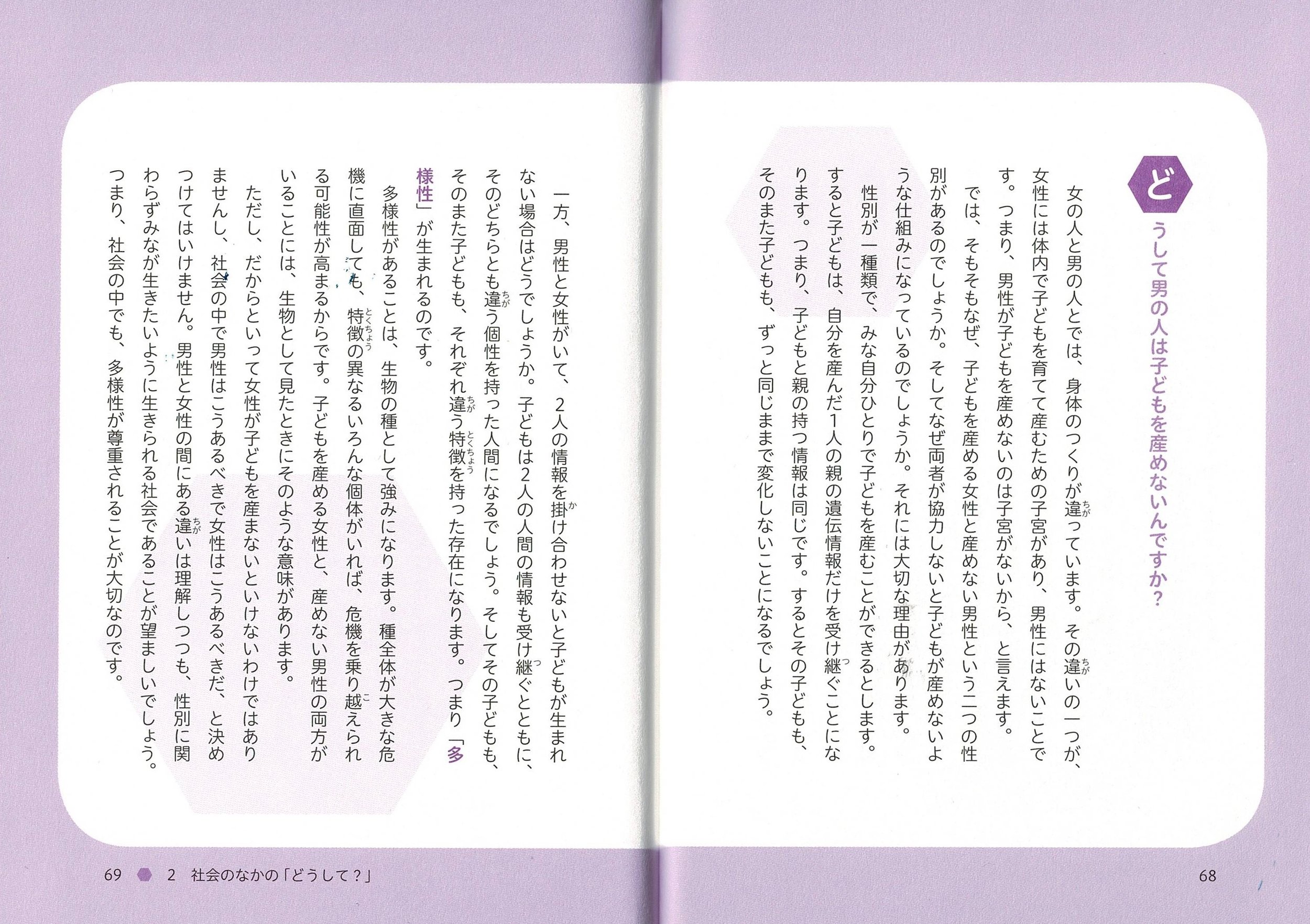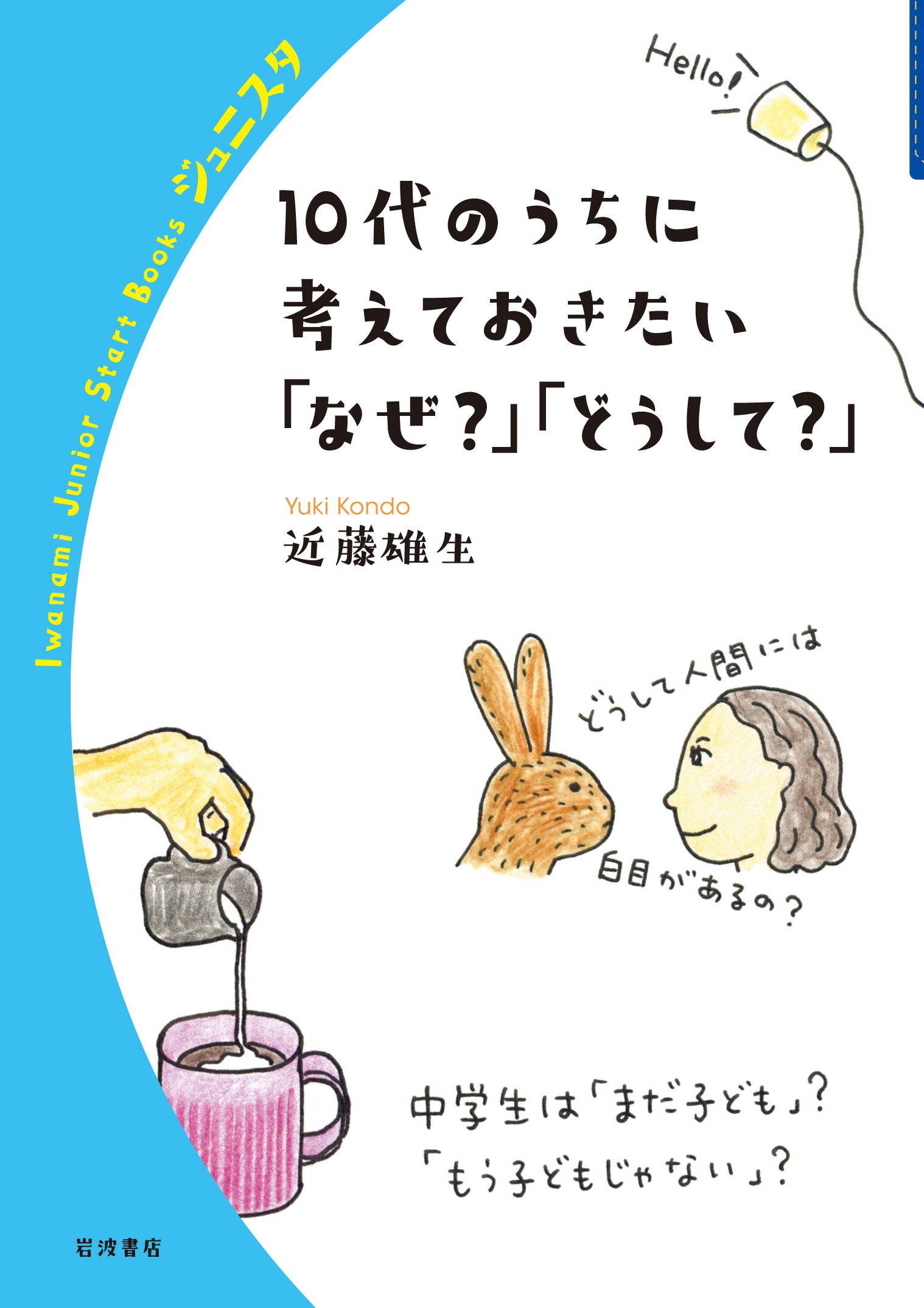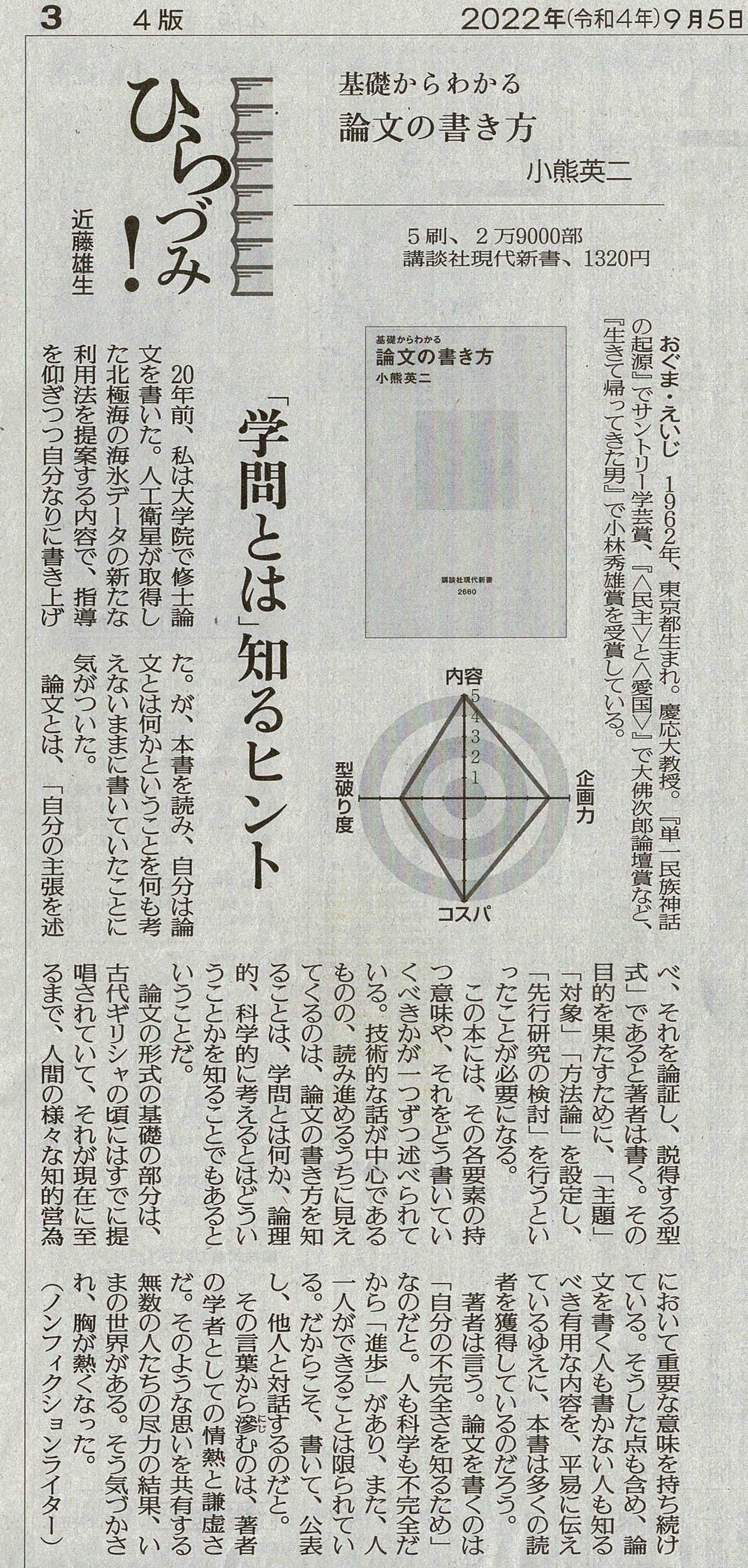20年以上のインドネシア占領の苦しい時代を残り超えて独立したのが2002年のこと。それから2年の国連軍による支援期間を終え、まさにこれから国として自立しなければならないという時期だった2004年5月11日、サッカーの全国大会「プレジデントカップ」の決勝戦が行われました。独立二周年の記念日を4日後に控えてのこと。
決勝戦の一方のチームの監督ジョンが、ぼくらが泊っていた宿に出入りしたことから知り合いになり、その縁で試合を観戦に行くことになったのですが、それは本当に、ずっと心に残る時間になりました。不透明な未来を前にそれぞれが複雑な気持ちを抱えつつも、スタジアムの内外には多くの人が集まり、熱狂する。そしてジョンが経てきた人生とサッカーへの情熱、それを影で支える宿のオーナー、オーストラリア人のヘンリー。さまざまなシーンやエピソードがいまも胸に迫ってきます。
そんなことを、10年以上前に出版した『遊牧夫婦』の中に書きました。自分自身、この本の中で一番好きな部分の一つでもあり、ふと思いたち、以下にその章「18 ジョンたちの決勝戦」(文庫版)を、写真とともにアップしました。中途半端なところからになりますが、よかったら読んでいただけたら嬉しいです。本に載せていない写真を複数掲載したので、すでに読んでくださってる人もぜひ。
ちなみに、ヨハンは、同じ宿に滞在していて親しくなった同年代のスウェーデン人。彼は東ティモールの政治について修士論文の執筆をしていて、ぼくは初めて依頼を受けての雑誌記事執筆中(東ティモールの独立2周年の様子について)。そしてエモンは宿で働いていたティモール人です。
以下、本文です。2022年10月時点での東ティモール代表のFIFAランキングは198位。ジョンの夢はまだ実現してないけれど、いまも彼の熱量が、そのまま心に刻まれています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
18 ジョンたちの決勝戦
ヨハンとともに三人で浮かれた日々を送りつつも、記事を書くための取材は少しずつ進めていった。ただ、企画が通ったあとで取材・執筆するというのはじつは初めてだったため、うまくできるだろうかという不安が少なからずあって、ぼくは何気に気が気ではなかった。
その点、ヨハンが身近にいたことで助けられた。彼はぼくらよりたしか一カ月ほど前から東ティモールに滞在していて、すでに研究のためのインタビューを重ねていたので、ぼくにとって大きな道しるべとなってくれた。
しかもヨハンの強気な取材方法は、物怖じしやすい自分を後押ししてくれた。驚かされたのは、彼がある政党の代表者だかをインタビューしようと、その人物に電話でアポを取っていたときのこと。キッチンで彼が携帯から電話するのを聞いていると、どうもインタビューに応じてもらえなそうな様子だった。するとヨハンはこんな感じでまくし立てるのだ。
「なんで、取材に応じてくれないんですか? ああ、そうですか、応じてくれないのなら、フレテリン(与党)の○×からのインタビューだけで、論文を書き上げてしまいますからね。それでもいいんですか? スウェーデンに偏った東ティモール事情が伝わることになりますよ」
驚くほど強気なのだ。もちろん彼が、影響力の大きな新聞やテレビの記者であるなら、言わんとしていることはわかるのだが、なにしろこれは一修士論文なのである。電話の相手になんと言われたのかは不明だけれど、「勝手にしてくれよ」と、あしらわれてもおかしくはない。
ひとりの大学院生としてヨハンがそう言っているのを聞いて、ぼくはただただ感心した。大メディアの人間がそんなことを言ったら、たちの悪い脅しのようにも聞こえてしまうが、修士論文のためのその主張は、ヨハンが、肩書きで相手を説得しているのではなく、自らの研究に誇りを持って取り組んでいることを表しているようにぼくには思えた。なるほど、そのくらい気持ちを込めて取材をするべきなのだろうと、すっかり鼓舞されたのだった。
実際に取材を始めると、思ったよりも人には会いやすかった。偶然出会った人やツテがある人に話を聞いていくというところから始めたが、その方法でかなりさまざまな立場の人と話すことができていった。
まずは、ヘンリーやヨハン、エモンとその友人たちといった身近な人からざっくりと状況を聞く。と同時に少しずつ範囲を広げ、日本料理店の主人とその店でたまたま出会った自衛隊員、ダイブショップを経営するイギリス人夫婦などにそれぞれの印象を聞いていった。ヨハンが築き上げていた人脈にも助けられた。
さらに、ふらりと大学に行けば、学生から話を聞けるし、その流れで大学の先生にも何人かインタビューできた。そのうちにだんだんと要領がつかめてきて、他に、JICAの駐在員、文部科学省から派遣された日本の役人、NGO職員、ジャーナリスト、現地の弁護士、ニューハーフらしい美容師さん、レストランの店員さんに服屋さん、路上で休む労働者、インドネシアのビジネスマン、といった具合に、話す相手をどんどん広げることができていった。